メルマガのクリック率やコンバージョン率(目標達成率)が思うように上がらず、頭を悩ませていませんか?
その原因は、ヘッダーとフッターにあるかもしれません。
この記事では、読者の反応を改善するために、メルマガのヘッダーとフッターに入れるべき要素を徹底解説!
さらに、有名企業の事例を参考にしながら、読者の視線を意識したデザインのコツを具体的にお伝えします。
この2つのパーツを最適化して、メルマガの効果を最大化させましょう!
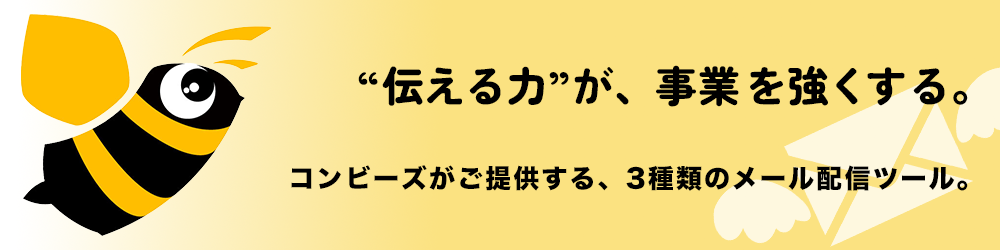
ヘッダー/フッターとは?
メルマガにおけるヘッダーとフッターは、それぞれメールの最上部と最下部に位置するパーツを指します。
これらは単なる飾りではなく、読者の反応を大きく左右する重要な役割を担っています。
メールを開いた瞬間に目に飛び込んでくるヘッダーは、誰からのメールなのかを伝え、続きを読むかどうかを判断させる「顔」のような存在です。
一方でフッターは、配信者の情報や配信停止手続きの方法など、法律で定められた項目を記載し、読者との信頼関係を築くための土台となります。
ヘッダーで興味を引きつけ、フッターで信頼性を担保することが、メルマガ全体の効果を高める第一歩です。
これらのパーツの役割を正しく理解し、適切に設定することで、開封後の読了率やクリック率の向上につながります。
メルマガのヘッダーに入れる要素
企業(サービス)名・ロゴ
ヤマト運輸のサイトはこちら
メルマガを開いた瞬間に「どこから届いたメールか」が分かることは、読者の安心感に繋がります。
特にHTMLメールの場合、見慣れたサービス名や企業のロゴが目立つ位置にあると、一目で送信元を認識してもらえます。
これは、数多くのメールが届く受信ボックスの中で、不審なメールと誤解されて読まれずに削除されてしまう事態を防ぐために非常に重要です。
ロゴや企業名をヘッダーの左上など、最初に視線が集まりやすい場所に配置するのが一般的です。
もし送信元がはっきりとしないと、たとえ有益な情報が書かれていても、不信感を抱かれてしまい、読み進められない可能性が高まります。
ブランドイメージを伝え、継続的に読んでもらうための第一歩として、企業(サービス)名・ロゴは必ず入れるようにしましょう。
お得な情報
NIKEのサイトはこちら
メルマガを開封してくれた読者の心を掴み「この先も読みたい」と思わせるためには、ヘッダー部分で得られるメリットを分かりやすく示すことが効果的です。
例えば、「本日23:59までタイムセール開催中!」といった緊急性の高い情報や、「7月の新商品ラインナップ」「今週の特集:夏を乗り切る快適ガジェット」のように、メルマガを読むことで得られる具体的なベネフィットを記載します。
このようなお得な情報が冒頭にあると、読者は自分に関係のある情報だと認識し、メール全体への興味が高まります。
特に、セールや限定キャンペーンなど、金銭的なメリットや希少性のある情報は、クリック率の向上にも直結しやすいです。
単に挨拶から始めるのではなく、読者が「このメールを読んで良かった」と感じられるような、魅力的な情報をヘッダーに盛り込むことで、メルマガの価値を高め、読者の関心を引きつけましょう!
メルマガが正しく表示されない時の対処法
星野リゾートのサイトはこちら
HTMLメールは、画像や装飾を使って視覚的に訴求できる反面、受信者の利用するメーラーやデバイスの環境によっては、レイアウトが崩れたり画像が表示されなかったりすることがあります。
せっかく作り込んだデザインも、正しく表示されなければ意図が伝わらず、読者にストレスを与えてしまいます。
こうした事態に備えて、ヘッダー部分に「メールが正しく表示されない方はこちら」といった一文を添え、メルマガと同じ内容を掲載したWebページへのリンクを設置しておくことが親切です。
この一工夫があるだけで、表示崩れが起きた場合でも読者はスムーズにコンテンツを閲覧でき、配信側は伝えたい情報を確実に届けることができます。
あらゆる受信環境を想定し、誰もが問題なく内容を確認できるような配慮が、読者の信頼に繋がります。
自社サイトへのリンク
@cosmeのサイトはこちら
メルマガの目的が、コンテンツを読んでもらうこと以上に、自社のECサイトやホームページへ読者を誘導することである場合、ヘッダーにサイトへのリンクを分かりやすく配置するのが有効です。
事例の「@cosme」のメルマガのように、企業ロゴやブランドのアイコン画像そのものに、トップページへのリンクを設定する方法があります。
読者は無意識にロゴをクリックすることがあるため、自然な形でサイト訪問を促せます。
ほかにも「公式サイトはこちら」「オンラインストア」といったテキストリンクを設置するのも良いでしょう。
このようにヘッダー部分をナビゲーションとして機能させることで、メルマガのコンテンツに深く興味を持つ前の段階でも、効率的に自社サイトへのアクセスを増やすことが期待できます。
メルマガのヘッダーデザインのコツ
ヘッダーサイズは600~700px
HTML形式でメルマガを作成する場合、ヘッダー画像のサイズは読者の閲覧環境を考慮して決めることが重要です。
スマートフォンやパソコンなど、様々なデバイスで快適に読めるようにするため、画像の横幅は600〜700ピクセルに設定するのが一般的です。
もし画像が大きすぎると、パソコンで見たときに横スクロールが必要になったり、スマートフォンでは画像の一部が見切れてしまったりする可能性があります。
逆に小さすぎると、伝えたい内容のインパクトが弱まり、読者の印象に残りづらくなってしまうでしょう。
レスポンシブデザインを採用している場合でも、この600〜700ピクセルという基準値を意識することで、表示崩れのリスクを減らし、どんな環境の読者にも意図した通りのデザインを届けやすくなります。
まずは基準となる600ピクセルで作成し、テスト配信で表示を確認してみるのがおすすめです。
左から右へ視線が動くのを意識する
Rakutenぐるなびのサイトはこちら
人が文章や画像を見るとき、無意識に視線は左上から右側へと流れていきます。
この自然な視線の動きを「Zの法則」と呼ぶこともあり、メルマガのヘッダーデザインにも応用できます。
読者がメルマガを開いて最初に目にするのはヘッダーの左上の部分です。
そのため、企業名やサービスのロゴといった、誰からのメールなのかを示す最も重要な情報は、ヘッダーの左端に配置するのが効果的です。
これにより、読者は瞬時に送信者を認識でき、安心して続きを読み進めることができます。
もし、ロゴの他にキャッチコピーやキャンペーン情報などを横並びで配置したい場合は、一番伝えたい要素を左側に、補足的な情報を右側に置くと良いでしょう。
例えば「左端にロゴ、右端にお得な情報や会員登録への導線」を設置すると、視線の流れがスムーズになり、読者にとってわかりやすいレイアウトになります。
この原則を意識するだけで、伝えたい情報が自然と読者の頭に入りやすくなります。
ブランドカラーを使う
ヘッダーデザインに自社のブランドカラーを取り入れることは、企業やサービスの認知度を高める上で非常に有効な手法です。
ブランドカラーとは、その企業らしさを象徴する特定の色を指します。
この色をヘッダーの背景やテキストに継続して使用することで「この色のメルマガは〇〇会社からだ」と読者に視覚的に印象付けることができます。
これにより、数多くのメールマガジンの中から自社のものを見つけてもらいやすくなる効果が期待できます。
全面的な背景色として大胆に使う方法もあれば、ヘッダーの上下にある罫線や、テキストの一部にアクセントとして使用するだけでも十分な効果があります。
大切なのは、ウェブサイトや他の広告媒体で使用している色と統一感を持たせることです。
一貫したカラー戦略は、読者の記憶にブランドイメージを定着させ、親近感や信頼感の醸成に繋がります。
配色の具体的なテクニックについては、以下の記事で詳しく紹介しています!
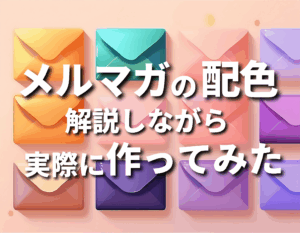
メルマガのフッターに入れる要素
特電法で載せることが定められているもの
メルマガのフッターを作成する上で、まず押さえておくべきなのが法律上のルールです。
「特定電子メール法」通称「特電法」と呼ばれるこの法律は、受信者の同意なく広告や宣伝メールを送ることを規制し、迷惑メールを防ぐために定められました。
この法律を守ることは、読者からの信頼を確保し、企業の誠実な姿勢を示す上で非常に重要です。
フッターには、この特電法によって定められた情報を必ず記載する必要があります。
| 送信者の氏名または名称 送信者の住所 受信拒否ができる旨の記述 受信拒否の手続きの連絡先(URLやメールアドレスなど) 問い合わせ先(電話番号、メールアドレスなど) |
以下はメルマガのヘッダーに記載した例です。
| ————————————————– 株式会社〇〇(ストア名:△△ショップ) 〒100-0005東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇ビル4F 【お問い合わせ】 メール:support@example.com 電話:03-1234-5678(受付時間:平日10:00~17:00) メールマガジンの配信停止をご希望の場合は、お手数ですが以下のURLからお手続きください。 配信停止はこちら:https://〇〇.com/〇〇 ————————————————– |
パッションリマインダー
ヤマト運輸のサイトはこちら
「このメールマガジンは、以前に弊社のサービスへご登録いただいた方にお送りしています。」
といった一文がフッターに記載されているのを見たことはありませんか。
これは「パーミッションリマインダー」と呼ばれるもので、読者に対して「なぜこのメールが届いているのか」を思い出してもらうための大切な役割を担っています。
多くの人は日々たくさんのメールを受け取るため、いつ、どこでメルマガに登録したのか忘れてしまうことも少なくありません。
そんな時に理由も分からずメールが届けば「迷惑メールかもしれない」と判断され、開封されずにゴミ箱に入れられたり、迷惑メール報告をされたりする可能性があります。
パーミッションリマインダーは、そうした事態を防ぐためのものです。
| 「このメールは、株式会社〇〇のメールマガジンにご登録いただいた皆様にお送りしております。」 「このメールは、過去に弊社サービスへお問い合わせ、または資料請求いただいた方へ配信しております。」 |
といったように、メールが届いた経緯を具体的に示すことで、読者は安心してメールを開封できます。
これは、読者からの信頼を得て、良好な関係を築くための簡単で効果的な方法です。
自社サイトへのリンク
NIKEのサイトはこちら
メルマガのフッターは、単なる結びの挨拶や署名欄ではありません。
読者がメルマガを読み終えた後に、次の行動へとスムーズに導くための重要な「導線」としての役割も持っています。
メルマガで紹介した商品やサービスに興味を持ってくれた読者がいたとしても、その熱量を次のアクションに繋げられなければ非常にもったいないです。
そこで活用したいのが、自社サイトへのリンクです。
フッターに公式サイトのトップページや、関連性の高い商品ページ、キャンペーンページへのリンクを設置しておくことで、興味を持った読者がすぐにアクセスできる環境を整えられます。
例えば「公式サイトはこちら」「開催中のセールはこちら」といった分かりやすい言葉でリンクを貼るのが効果的です。
メルマガの内容だけで完結させるのではなく、読者がさらに情報を深掘りしたり、購入を検討したりするための入り口を用意しておくことが、クリック率やコンバージョン率の向上に繋がります。
フッターを戦略的に活用し、読者を自社のウェブサイトへ誘導する仕組みを作りましょう。
SNSアカウント
GUのサイトはこちら
現代のマーケティングでは、メルマガだけでなく、SNSなど複数のチャネル(媒体)を通じて顧客と接点を持つことが重要です。
フッターに自社で運用しているSNSアカウントへのリンクを設置することで、読者との繋がりをさらに深めることができます。
メルマガは定期的な情報発信に、SNSはリアルタイムな情報や、よりカジュアルなコミュニケーションに適しているなど、それぞれに得意な領域があります。
メルマガ読者にSNSもフォローしてもらえれば、メルマガを配信していない日でも、新商品の情報や日々のちょっとした出来事などを通じて、顧客との関係を維持し、強化することが可能です。
HTMLメールを利用している場合は、LINE、X(旧Twitter)、Facebook、Instagramといった各種SNSのロゴアイコンにリンクを設定するのが一般的です。
視覚的に分かりやすく、直感的なクリックを促すことができます。
これにより、メルマガ配信だけでは伝えきれない情報も届けられるようになり、顧客が自社のファンになってくれる機会損失を防ぐことに繋がります。
メルマガのフッターデザインのコツ
本文よりフォントサイズを小さくする
出前館のサイトはこちら
メルマガのフッターは、補足的な情報を掲載する場所です。
そのため、メインコンテンツである本文よりもフォントサイズを小さく設定し、情報の重要度に応じて見た目に差をつけるのが一般的です。
本文と同じ大きさの文字がフッターにまで続くと、どこまでが本編なのか分かりにくく、読者にストレスを与えてしまう可能性があります。
ただし、フォントサイズを小さくしすぎないよう注意が必要です。
特にスマートフォンで閲覧する場合、文字が小さすぎると非常に読みにくくなります。
一般的に、15pxを下回ると指で拡大しないと読めないケースが増えるため、最低でも15px程度のサイズを確保すると良いでしょう。
受信環境によっても見え方は変わるため、配信前には必ずテスト配信を行い、スマートフォンでの表示崩れや読みにくさがないかを確認することが大切です。
本文ブロックと差別化する
GQJapanのサイトはこちら
フッターが本文の一部であると誤解されないよう明確に区別することが重要です。
本文ブロックとの境界線をはっきりと示すことで、読者は「ここが記事の終わりだな」と直感的に理解でき、スムーズに読み終えることができます。
差別化するための最も簡単な方法は、本文ブロックとフッターの間に一本のライン(罫線)を引くことです。
シンプルな線でも情報の区切りとして十分に機能します。
また、フッター全体の背景色を本文とは異なる色に変えるのも効果的です。
会社のロゴやSNSへのリンクアイコンなどを区切りとして配置するデザインも、多くの企業で採用されている定番の手法です。
メルマガのヘッダー・フッターのデザイン事例
kate spade new york
・ヘッダー
kate spade new yorkのサイトはこちら
シックでおしゃれなアパレルブランド、kate spade new yorkのメルマガは、ECサイトへの誘導を強く意識した構成が特徴です。
ヘッダー部分には、ブランドロゴと共にECサイトへ直接アクセスできるリンクが分かりやすく配置されています。
例えば「秋のラインナップ」といったように、メルマガのテーマをヘッダーで明確に伝えることで、読者は一目で内容を把握できます。
さらに「こちら」や「SHOP NOW」といった行動を促す文言に下線を用いることで、クリックできるリンクであることが直感的に伝わるよう工夫されています。
これは、読者をスムーズに目的のページへ導くための、細やかですが重要な配慮です。
・フッター
フッターも、読者の利便性を高める設計になっています。
「新作」や「セール」など、興味のあるカテゴリーへ直接飛べるリンクが整理されており、回遊性を高める工夫が見られます。
情報量が多くなりがちなフッターですが、十分な余白を取り、黒で統一されたシンプルなアイコンを使用することで、洗練されたブランドイメージを損なわないデザインに仕上げています。
星野リゾート
・ヘッダー
星野リゾートのサイトはこちら
星野リゾートのメルマガは、ブランドの世界観を巧みに表現しつつ、読者の利便性を追求したデザインが参考になります。
ヘッダーには、画像が表示されない受信環境の読者に向けた「画像が表示されない方はこちら」というテキストリンクが設置されており、誰にでも情報が届くよう配慮されています。
また、特徴的なロゴのフォントは、星野リゾートのブランドイメージを確立する重要な要素です。
「星野リゾートメールマガジン」というロゴを配置することで、予約確認メールなど他のメールと区別できるように工夫されています。
・フッター
フッターは、読者の目的を予測して設計されている点が秀逸です。
| ・「空室検索」をしたい人 ・「旅のテーマ」を探したい人 ・「星野リゾート」についてもっと知りたい人 |
それぞれのニーズに応えるための導線が用意されています。
このように複数のリンクを設置する場合、リンク同士の間に十分な余白を確保することが大切です。
これにより、押し間違いを防ぎ、ストレスのない操作性を実現しています。
アイコンの色を白で統一し、背景色とのコントラストをはっきりさせることで、視認性とデザインの一貫性を両立させています。
Nintendo(任天堂)
・ヘッダー
Nintendoのサイトはこちら
Nintendoのメルマガは、ブランドイメージである「楽しさ」や「親しみやすさ」が伝わるデザインになっています。
ヘッダーは、ブランドカラーである赤を基調とし「ほしい物リストセールのお知らせ」のように、メルマガの目的がひと目でわかる見出しが記載されています。
これにより、読者は自分に関係のある情報かどうかを瞬時に判断でき、開封後の読了率を高める効果が期待できます。
・フッター
フッターは、アイコンや区切り線を効果的に使い、情報を整理しています。
本文との境界を明確にするため、フッター全体の背景に薄い赤色を設定しているのも、見やすさを高める工夫の一つです。
SNSのアイコンについては、各SNSの公式カラーをそのまま使用しています。
これは、Nintendoの「直感的に理解できること」を重視するデザイン哲学の表れと考えられます。
誰にとっても馴染みのある色だからこそ、一目で何のSNSか分かりやすいのです。
スタイリッシュさよりも、ブランドが大切にする「分かりやすさ」や「親しみやすさ」を優先したデザインと言えるでしょう。
復習テスト!
この記事では、メルマガの成果を最大化するために不可欠なヘッダーとフッターの役割、入れるべき要素、そしてデザインのコツを解説してきました!
記事の内容を○×クイズにしました。ぜひ復習につかってみてくださいね!
| 問題番号 | 問題文 |
| 1 | メルマガのヘッダーは、主に配信停止手続きの方法を記載し、読者との信頼関係を築くためのパーツである。 |
| 2 | メルマガのフッターには、「特定電子メール法」により、送信者の氏名または名称と住所を記載する必要はない。 |
| 3 | 読者の興味を引くために、ヘッダーには「タイムセール開催中!」といったお得な情報を載せると効果的である。 |
| 4 | HTMLメルマガのヘッダー画像の横幅は、様々なデバイスで見やすいように1000px以上で作成するのが一般的である。 |
| 5 | 「このメールはメルマガに登録いただいた方へお送りしています」という一文(パーミッションリマインダー)は、読者に安心感を与える役割を持つ。 |
| 6 | フッターの文字サイズは、本文と同じサイズに設定し、デザインの統一感を出すのが良いとされている。 |
| 7 | フッターに自社のSNSアカウントへのリンクを設置することは、読者との繋がりを深める上で有効な手段である。 |
| 8 | 人の視線は右上から左下へ動く傾向があるため、最も重要な企業ロゴなどはヘッダーの右端に配置するのが効果的である。 |
| 9 | HTMLメールが表示崩れした場合に備え、「正しく表示されない方はこちら」というWebページへのリンクをヘッダーに設置することが推奨される。 |
| 10 | フッターの役割は法律で定められた項目を記載することだけであり、自社サイトへのリンクなどを設置して読者を誘導するべきではない。 |
解き終わったら以下の回答をどうぞ!
| 問題番号 | 回答 | 解説 |
| 1 | × | ヘッダーは、誰からのメールかを示し、続きを読むか判断させる「顔」の役割を持ちます。 配信停止などは主にフッターの役割です。 詳しい解説 |
| 2 | × | 「特定電子メール法」により、送信者の氏名(名称)、住所、受信拒否の通知先などをフッターに明記することが義務付けられています。 詳しい解説 |
| 3 | ◯ | ヘッダーに読者のメリットとなる情報を載せることで、メール全体への興味を高め、クリック率の向上に繋がります。 詳しい解説 |
| 4 | × | 様々な閲覧環境を考慮し、ヘッダー画像の横幅は600〜700ピクセルに設定するのが一般的です。 詳しい解説 |
| 5 | ◯ | なぜメールが届いたのかを読者に思い出してもらい、迷惑メールと誤解されるのを防ぐことで、信頼関係を築く効果があります。 詳しい解説 |
| 6 | × | フッターは補足的な情報を掲載する場所なので、本文よりフォントサイズを少し小さくして、情報の重要度に差をつけるのが一般的です。 詳しい解説 |
| 7 | ◯ | メルマガ以外の接点を持つことで、顧客との関係を維持・強化し、自社のファンになってもらう機会を増やすことができます。 詳しい解説 |
| 8 | × | 人の視線は無意識に左上から右側へと流れる(Zの法則)ため、企業ロゴなど最も重要な情報はヘッダーの左端に配置するのが効果的です。 詳しい解説 |
| 9 | ◯ | あらゆる受信環境を想定し、誰もが問題なく内容を確認できるよう配慮することが、読者の信頼に繋がります。 詳しい解説 |
| 10 | × | フッターは、読者が次の行動へ移るための重要な「導線」の役割も持ちます。自社サイトへのリンク設置はコンバージョン率向上に有効です。 詳しい解説 |
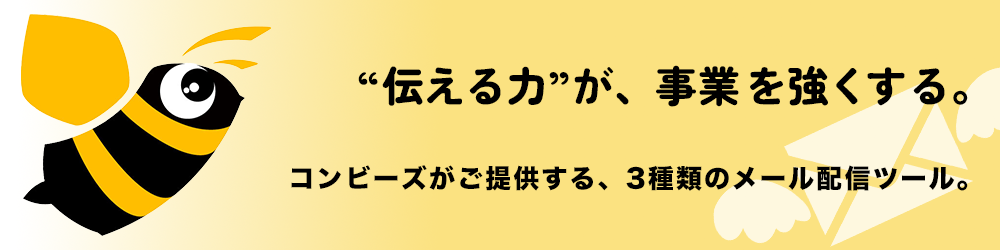
この記事を書いた人
宇都宮凛奈
コンビーズの公式XとYouTubeショートを担当しているりんりんです!
こんびーちゃんとお仕事をしたりおやつを食べてます。
ライターとしてまだまだ修行中!
いろんなデザインを見たり、空と海の写真を撮るのが趣味。
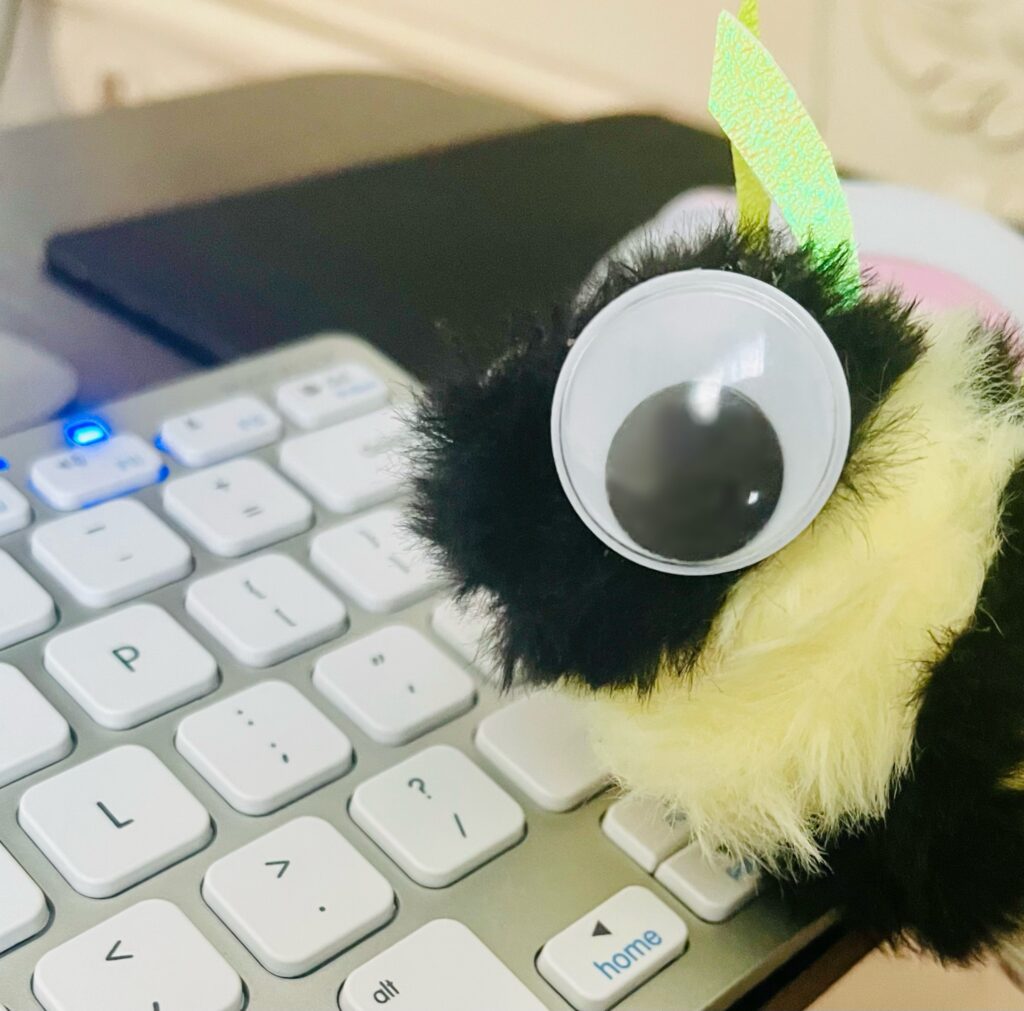


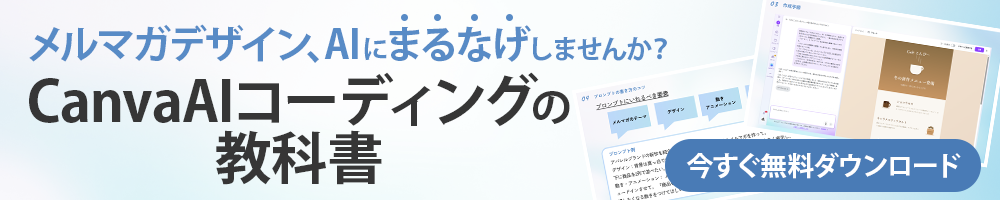
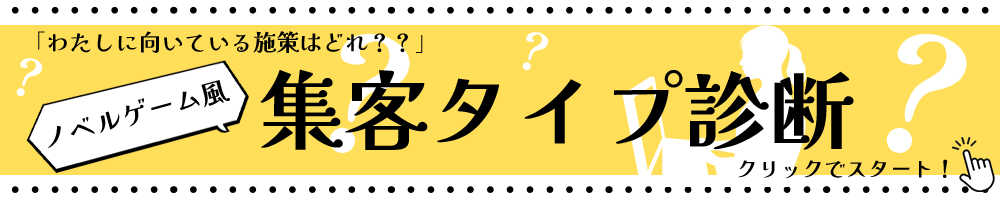





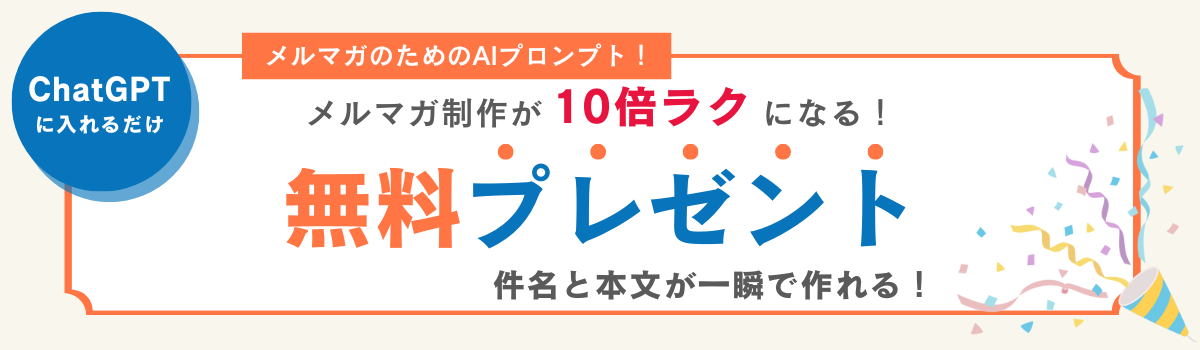
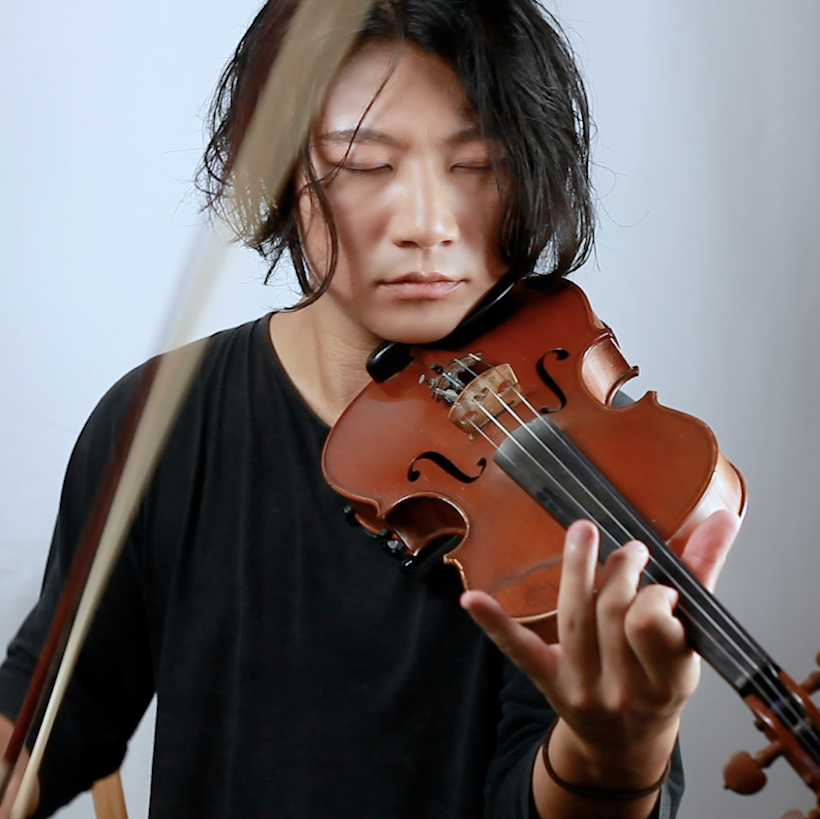

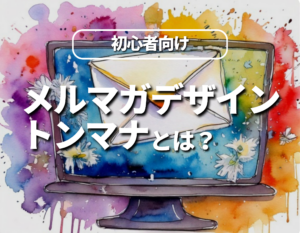
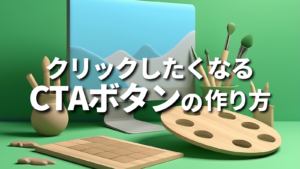
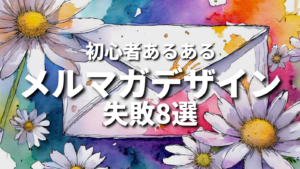
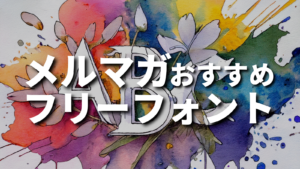


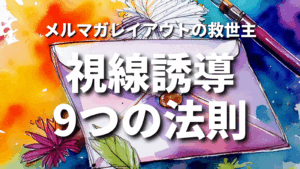
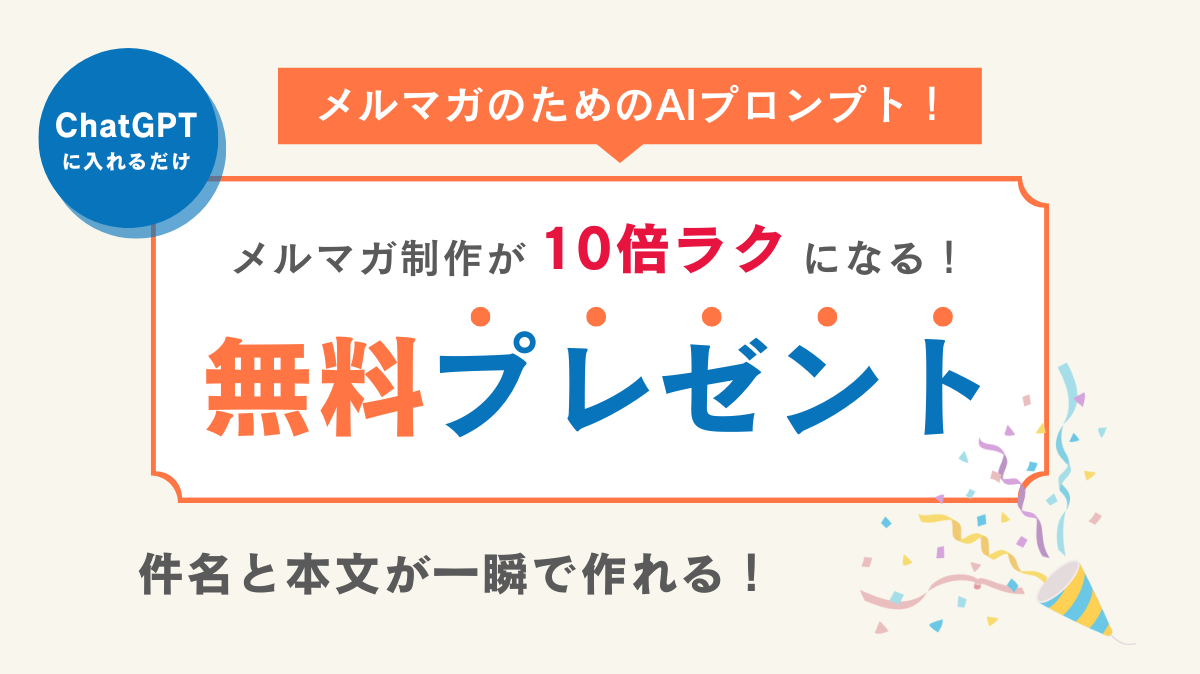
コメント